Dítě v mlze
(霧の中の子ども)

著 者:マルチン・ゴファ
Martin Goffa
表 紙:パヴェル・カドゥレツ
Pavel Kadlec
発行年:2016年
出版社:Mladá fronta
頁 数:224
ISBN :978-80-204-4103-4
ミコ(ミクラーシュ)・スィロヴィー
Miko (Mikuláš) Syrový シリーズ
01. Muž s unavenýma očima (2013)
(疲れた目をした男)
02. Bez těla (2014)
(見つからぬ遺体)
03. Mezi dvěma ohni (2014)
(二つの炎のはざまで)
04. Živý mrtvý a další policejní
povídky (2015)
(生ける屍者 ー 短編警察小説集)
05. Plaváček (2016)
(漂う人形)
06. Dítě v mlze (2016)
(霧のなかの子ども)本書
07. Štvanice (2017)
(マンハント)
08. Vykoupení (2018)
(償い)
09. Primární důvěra -
prst na spoušti (2019)
(根本的信頼 ー
引き金にかけられた指)
10. Primární důvěra -
úhel pohledu (2019)
(根本的信頼 ー
物事を見る角度)

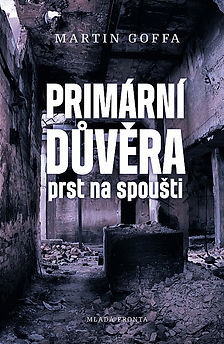

〔解 説〕
7歳の少年が小学校から誘拐された事件は、むごたらしいものになると思われたが、通常とはまったく違う展開を見せ始める。誘拐犯は連絡もなんらの要求もよこさないなど、捜査が進むにつれ、その異例さが明らかになっていく。しかも捜査陣をあざ笑うかのごとく、犯人は早い段階で自分の顔を公開したのだ。犯人は元相棒のベルトと判明したため、ミコ・スィロヴィーもしぶしぶ捜査に協力するはめになる。刑事が刑事を追う。だが犯人は自分の経験を活かして常に一歩先を進む。そして「痛みには痛みを」という明白過ぎる彼のメッセージが……(裏表紙の内容紹介より)
2016年イジー・マレク賞(*)受賞
* 国際推理作家協会のチェコ支部がチェコの年間最優秀ミステ
リに贈る賞
〔Neklan 一言〕
ミハエラ・クレヴィソヴァーの『殺人者の足音』に続く《チェコの最新ミステリの傑作を発見せよ!(仮題)》第二弾は、マルチン・ゴッファの《ミコ(ミクラーシュの略称)・スィロヴィー》シリーズ第6作、2016年のイジー・マレク賞の受賞作である『霧の中の子ども(Dítě v mlze)』です。
マルチン・ゴッファ(1973 - )は元警官の匿名作家のペンネームで、WEB誌 Vaseliteratura.cz のインタビューによると、25歳までは一般の技術系の仕事についていましたが、給料に不満があったことから友人の勧めに従って警察に転職。以降15年間の奉職期間のうち最初の3年は制服警官として、残る12年は刑事として主に窃盗を担当し、経済犯罪の捜査に携わった経験もあるそうです。
2013年に《ミコ・シロヴィー》シリーズの第1作『疲れた目をした男(Muž s unavenýma očima)』でデビュー。一躍注目作家となり、翌14年には同シリーズの新作二本『見つからぬ遺体(Bez těla)』と『二つの炎のはざまで(Mezi dvěma ohni)』を発表するというハイペースな仕事ぶり。以後このシリーズは2019年までに十作が発表されています。
2019年からはジャーナリストのマルチン・ヴラースを主人公にした新シリーズを開始。こちらは2022年に第6作が出版されました。その他にどちらのシリーズにも属さない作品がひとつあります。
マルチン・ゴッファは読書好きではあるものの、ミステリにはあまり興味がなく、近年世界中で流行している北欧産のミステリも読んでおらず(スティーグ・ラーソンの大ベストセラー《ミレニアム》シリーズも未読との由)、読んだことのあるミステリはクリスティの『そして誰もいなくなった』とエドガー・アラン・ポーの短編を数編といった程度。ジャンル作品よりもドストエフスキーやヴィクトル・ユーゴー、トーマス・マンといったメインストリームの文学作品でミステリの要素があるものを好み、好きな作家はウィリアム・スタイロン、ウンベルト・エーコ、ジェームズ・クラヴェルだそうです。
シューヴァル&ヴァールーの《マルティン・ベック》シリーズや、ル・カレの作品といった暗く重く救いのない社会派ミステリが大好きな Neklan としては、誘拐がテーマで、レビューを読むと「救いがない」という感想が多く見られ、しかもイジー・マレク賞の受賞作となれば、面白さは保証済みと期待に胸を膨らませて読み始めました。唯一の懸念材料は短いこと。ミハエラ・クレヴィソヴァーの『殺人者の足音』が360ページあるのに対して、こちらは224ページしかない。当HPでこれまで紹介した長編で一番短いのがホラー『囚われの少女』の236ページですから、それよりもまだ短い。「それはいくらなんでも、扱っている題材が誘拐という深刻なものだけに、ちと短か過ぎるのでは?」と。
結論から言うと、不安は的中。中味が薄い。
誘拐ものとなれば、犯人と警察の丁々発止の頭脳戦とか、犯人と被害者の関係の変化とか、なんらかの原因でタイムリミットがあるとか、定番とはいえハラハラドキドキの要素が幾つもあるにもかかわらず、この作品では全体的に書き込みが足らないため、犯人が警察をだし抜く件(くだり)や、犯行におよんだ同情すべき理由、救いのない結末等は一応書かれてはいるものの、それがこちらにちっとも響いてこない。長めのプロットを読まされている感じ(ドラマ・映画にするにはこのぐらい緩い方がアクションシーンを盛り込めるので、いいかもしれませんが)。
しかも主人公のミコ・シロヴィーが誘拐担当ではないため捜査の指揮は別の刑事クーンツが行い、ミコの役割はもっぱら犯人で元相棒のベルト(ベルトフスキーの略称)との過去の関係を思い出し、クーンツに情報・助言を与えていくだけ。作者のマルチン・ゴッファは元警官なので、管轄を越えた越権捜査は事実に反するから描けないということなのでしょうが、これでは話が盛り上がらないこと甚だしい。
また、これは『殺人者の足音』を読んだ時にも同様に感じたことですが、『霧の中の子ども』も警察小説の態をとってはいるものの、捜査チームとしては描かれておらず、せいぜい主人公の相棒が話し相手になるぐらい。マルティン・ベックにはコルベリ、ラーソン、メランデル、ルンといった個性豊かな同僚刑事たちがいて、それぞれに得意分野があり、たとえ刑事としては凡庸な者でも特定分野においては優れた能力を発揮し、時に事件解決に重要な役割を果たしていたのに較べると雲泥の差。物足りない。物足りないぞ。
どうしてこのような作品がチェコの読者からもプロたちからも高い評価を得ているのか、理解に苦しむ Neklan でした。ドストエフスキーやヴィクトル・ユーゴー、トーマス・マン、ウィリアム・スタイロン、ウンベルト・エーコ等の影響を受けているというなら、彼らにならってもっと重厚な作品を書いてくれよと思うことしきり。調べたところ、マルチン・ゴッファの作品はどれも200ページちょっとで、しかも年二作発表という年が何度もあるので、腰を据えてじっくり書き込んでいくタイプの作家ではないのでしょうね。
正直、チェコの小説を読んで、これほど失望したのは初めての経験で、期待が大きい作品だっただけに残念です。
